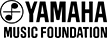研究・レポート
研究・レポート
小川 容子(おがわ ようこ)
岡山大学大学院 教育学研究科 教授
※記事掲載時点の情報です
「音感(おんかん)」は測れるのか
2013年11月07日掲載 / この記事は約10分で読めます
岡山大学大学院教授 小川容子先生による「音感」をテーマにしたレクチャーシリーズの第2回。音楽を愛好する皆さんにとって、「音感」はなじみが深い言葉です。しかし小川先生によれば、実は「音感」は学術的に定義付けることの難しい言葉。なぜ難しいのでしょうか? その背景を知る手がかりとして、前回は音楽心理学において耳や聴覚に関する研究がどう展開してきたかをご説明いただきました。 前回のレクチャーによれば、今からおよそ100年前、アメリカの心理学者シーショア(Carl Emil Seashore)が発表した「耳の力」を測定するためのテスト※1を端緒として、さまざまな音楽テストの開発が試みられるようになりました。中でも長期にわたってその研究を展開したのがゴードン(Edwin E. Gordon)※2です。今回は、彼のつくった音楽テストについてのお話からうかがいたいと思います。
――前回のレクチャーでは、シーショアの研究以後、ある耳の力に関して新しい音楽テストを使った実験が行われるたびに、そのテストが耳の力の何を測っているのかが論争になる、ということでした。そうして開発されたさまざまなテストの中でも、ゴードンのつくったものは有名ですね。
小川教授(以下、敬称略):そうですね。前回お話した通り、「音感」は日本語であり、一言で翻訳できる言葉ではありません。「You have a good ear for music(良い耳を持っている)」と言い換えたとしても、「良い耳」も一様にはとらえられません。耳の力や音楽の力を測るテストにおいても、研究者たちはみんないろいろな言葉を使ってきました。シーショアが積み上げたものを、他の研究者が引き継ぐというのではなく、既存のものを1回壊して、別の形の音楽テストをつくり、おのおのが違う言葉を使って論じてきたのです。 大学の学部1、2年生を対象とする講義では、研究者によって異なる定義付けがなされてきて、結局のところ共通見解がないという歴史的な背景を中心に説明するようにしています。3、4年生以上になったら、一応主流になってきたテストのひとつとして覚えておきましょうということで、ゴードンのテストを紹介します。
――ゴードンはどんな言葉を使っているのですか?
小川:ゴードンの音楽テストは「Musical Aptitude Profile(MAP)」、すなわち「音楽適性プロフィール」といいます。日本語の四字熟語としても「音楽適性」なんて聞き慣れないですよね。音楽心理学の分野では、一般的に潜在的にもっている音楽の力を「適性(Aptitude)」と呼んで、学習して身につく「学力(Achievement)」とは区別しています。日本語で非常に大ざっぱにいうならば、どちらも「音感」と言えなくもないでしょう。しかし、日本語では「音楽適性」を「音感」という大枠でくくることができても、ゴードンのいう「Aptitude」やほかの研究者がいう「Ability(能力)」「Achievement」といった言葉は、「音感」にぴたっと当てはまる英訳ではありません。日本人の研究者による論文で「音感」という言葉が出てこないのは、そこでいう「音感」とはAptitudeなのかAchievementなのか、その都度説明しなければならず、混乱を招くからです。
――なぜゴードンのテストが、音楽心理学の分野で主だった音楽テストのひとつに位置付けられるようになったのですか?
小川:音楽テストの研究は、実験を繰り返して標準化するまで、何度も検討を加えなければいけません。それはとても大変で気の遠くなるような作業です。通常、テストの標準化までに10年以上はかかるといわれています。ゴードンは、根気強くこの研究を続けたのです。
――一般に心理学では、多くの実験とじゅうぶんな理論的検討を経て、テストに関する厳密な規定が決定されるまでの一連の手続きを標準化と呼んでいますね。
小川:そうです。たとえば、岡山大学の学生を対象に実験をして、そのテストでは「測るべき耳の力」を正確に測定できているという結果が、仮に得られたとします。しかし、ほかの大学の学生を対象にしたら、小学生を対象にしたら、あるいは同じ小学生でも私立の学校と公立の学校だったら、全く異なる結果になるかもしれません。新しい音楽テストで実験を繰り返しながら、問題に偏りが無いか、適切な問題か、難しい問題は「本当に難しく」、易しい問題は「本当に易しいのか」など、改訂に改訂を重ねる必要が出てくるのです。 ゴードンの場合、意欲的に次々と改訂版を発表し、さらに海外でも実験を行いました。彼はアメリカの研究者ですが、彼のテストがアメリカ以外でも実施可能なことを明らかにし、テスト用のCDやマニュアルも作成しました。その結果、音楽適性といえばゴードンだというような流れを定着させていったのです。
| Test T:音のイメージ | Test R:リズムのイメージ | Test S:音楽的感受性 |
パート1:旋律
パート2:ハーモニー | パート1:テンポ
パート2:拍子 | パート1:フレーズ
パート2:バランス
パート3:様式 |
――ゴードンの音楽テストは、旋律やリズムなどの音楽要素別にテスト項目が挙げられていますが、小川先生も研究の一環として音楽テストを作成なさっていますね。
小川:はい。ゴードンのテストはもちろん、その他の先行研究も参考にしながら、「新アジア版音楽適性テスト」というものを作成しました。私がゴードンの研究で着目したのは、「Aptitude(適性)は潜在的なものだ」という点です。彼の研究では、Aptitudeはポテンシャル(潜在的な可能性)であって、かつ計測可能だというところから始まり、それが9歳ごろまで発達するという考え方に基づいています。 私たちは「生まれてから何ら特別な音楽的経験を受けていない」といったとしても、日常的にはいろいろな音楽経験をしています。ヤマハ音楽教室に通えば、当然「音楽の学習をしています」とか「音楽経験があります」と言えるけれども、通っていなくても、テレビを見たり、お父さんやお母さんが買ってきたCDを聞いたり、あるいは学校へ通うようになれば、いろいろな形の音楽環境があり得るわけです。そこで、9歳、つまり小学校3年生くらいの段階にかけて、ある種の上達曲線は描くだろうというゴードンの主張は参考になる部分があると思いました。
――なぜゴードンの音楽テストをそのまま使って実験するのではなく、新しいテストを作成する方法をとったのですか?
小川:子どもたちが日常的に音楽に触れることで潜在的な耳の力が育っていると考えたとき、私たちは日々の音楽環境、つまり西洋音楽も聴いているけれど、日本の音楽もよく聴いているという環境を考慮しました。今までにつくられた音楽テストというものは、どれも西洋音楽の枠組みにのっとっています。しかし、ご高齢の方が家族にいたら子どもたちは演歌もよく聞いているかもしれないし、小学校でも以前よりさかんに日本の音楽が教えられるようになっています。私たちがつくった適性テストでは、パート5が特徴的な内容になっていて、意図的に西洋音楽ではない旋律を聴く項目が含まれています。
――ゴードンの音楽適性プロフィールや小川先生の新アジア版音楽適性テストでは、テストの項目が音色や音量、旋律といった項目に分かれていますが、そうした「音楽要素を聴き取ることができること」=「音感」ととらえられるのでしょうか?
小川:「言えなくはない」というくらいに思っています。たとえば旋律の問題であれば、いくつかの音源を聴き、核となる旋律を聴き取っているかが問われます。クリスマスツリーを思い浮かべてみてください。たくさんのオーナメントで飾られたクリスマスツリーは、もともとはもみの木です。飾りのついたもみの木と、飾りの外されたもみの木を比べて、それらが同じもみの木であることに気が付けるかどうか、つまり装飾を外して元となっている旋律を聴く力があるかが重要です。 この力を音感だと定義付けるのではなく、私は「これが音感ですか?」という質問に対しては、「音感に含めてもいいかもしれませんね」とお答えしたいと思います。音色の違いが聴き取れること、音量やピッチの違いを聴き取れることについても同じです。人によってさまざまな考え方がありますので、たとえばわずかなピッチの違いがわかることを重要視する方がいらっしゃったら、「それも音感のひとつに入れていいかもしれない」ということはできるかもしれません。しかし、ピッチの違いがわからないからといって、その人には「音感がない」ということは少し違うのではないかと思います。
――ピッチの違いがわかるかどうかというと、「絶対音感」が関係してくるのでしょうか?
小川:確かに専門的に音楽を習うに当たり、「絶対音感が身に付くかどうか」ということが話題になることがありますね。「絶対音感がある」というと、絶対的な音の高さを何らかの音名で言い当てるという能力がついているかのように理解されたりします。
注意しなければならないのは、「音感」は定義付けられない言葉ですが、絶対音感(absolute pitch)には定義があるということ、しかも、この音感は「点」ではなくて、ある「幅」を持っているということです。絶対音感について、これまでの研究でさまざまなデータが提示されていますが、「絶対音感の有無」のとらえ方は研究者のスタンスによるところがあります。440ヘルツの「ド」の音と439ヘルツの「ド」の音の違いがわかる人もいれば、「ド」と「ド♯」の半音の違いならばわかる人、バイオリンの音色だと聞き取れないけれどピアノの音ならばわかる人など、実際にいろいろな事象があることがわかっています。本当はそういった細かい定義付けをしなければ、絶対音感の有無は簡単に言い切れるものではありません。また、音の高さについては、前後の音を聴き比べて、どちらの音の方が高かったか低かったかがわかる、音程感というのも大切ですね。
たとえ専門的な音楽教育であっても、絶対音感を身に付けるために「ド」の音を覚えるのではなく、楽しくレッスンを続けることの方が、意味が大きいと思います。先ほど申し上げたように、「ド」の音がわかるといっても幅がありますし、絶対音感の有無と音感があるかないかはあくまで別のお話です。絶対音感の有無は、音楽を親しむうえではひとつの側面にすぎないということですね。
――どうもありがとうございました。「音感」や「絶対音感」のお話をとおして、改めて音楽の聴き方や聴く力にはさまざまな考え方があることがわかります。次回は絶対音感のお話の続きからお伺いしたいと思います!
- ※1 シーショアは1919年に音楽才能テスト(Measures of Musical Talent)を発表、その後1939年と1960年には改訂版も作成した。
- ※2 ゴードンは国際的に著名な研究者、教育家であり、1960年代からこれまでに9つの標準化された音楽テストを発表しているほか、活発な執筆活動を行っている。
聞き手:ヤマハ音楽研究所研究員 小山文加(おやまあやか)
著者プロフィール ※記事掲載時点の情報です
小川 容子(おがわ ようこ)
岡山大学大学院 教育学研究科 教授
専門:音楽教育、音楽認知心理学
著書・論文
- 音楽する子どもをつかまえたい:実験研究者とフィールドワーカーの対話 2008年,ふくろう出版
- 音楽教育学の未来 -日本音楽教育学会設立40周年記念論文集 2009年,音楽之友社
監訳書
著書・論文
- 音楽する子どもをつかまえたい:実験研究者とフィールドワーカーの対話 2008年,ふくろう出版
- 音楽教育学の未来 -日本音楽教育学会設立40周年記念論文集 2009年,音楽之友社
監訳書
今後より一層内容の充実を図るため皆さまからのご意見・ご要望をお聞かせいただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。(全12項目)