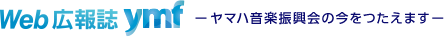「すべての人がもっている音楽性を育み、自ら音楽をつくり、演奏し、楽しむことのできる能力を育て、その音楽の歓びを広くわかちあう」ことを教育理念とするヤマハ音楽振興会が、中学生以下のピアノ学習者を対象に、学習と研鑽、および若きピアニスト育成の場として展開している「ヤマハジュニアピアノコンクール(YJPC)」(主催:㈱ヤマハミュージックジャパン、共催:ヤマハ音楽振興会)。「即興演奏」「編曲演奏」「創作」などの教育に力を入れ、将来幅広い音楽活動ができる人材育成を目指してきたヤマハの理念に基づき、音楽のジャンルを問わないことや、編曲演奏を課題に含むなど、演奏曲の自由度や幅広さが本コンクールの特長となっています。
2016年からスタートし、第4回となる今年は2019年7月23日(火)24日(水)の両日、紀尾井ホール(東京都千代田区)にてグランドファイナルが開催されました。全国6エリアでのエリアファイナルを通過した38名が出場し、課題曲、課題編曲、自選曲を演奏。厳正な審査の結果、B、C、D各部門の入賞者がそれぞれ選ばれました(A部門はエリアファイナルが最終審査)。
満15歳以下を対象としたD部門には9名が出場。課題曲、課題編曲、自選曲を出場者自身が決めた曲順で演奏し、日頃の練習の成果をいかんなく発揮しました。その中から第1位に選ばれた、大同 理紗さんの喜びの声をご紹介します。
D部門第1位:大同 理紗さん(15歳)のコメント
今日は精いっぱい自分を出し切ろう、と思いながら楽しく弾きました。ベートーヴェンは歌い過ぎるとロマン派の楽曲のようになってしまうし、あまりにも控えめだと味気ないので、時代にあわせた表現ができるように強弱の変化や音色を工夫しました。リストは以前から弾いていてとても好きな曲です。弾く側は大変でも、聴いてくださる皆さんが難しそうだな、大変そうだなと感じないようにスマートに弾くよう努めました。今日は自分のカラーが出せたと感じています。課題編曲のサン=サーンスは、何度も出てくる同じテーマをリハーモナイズして変化をつけて仕上げました。
これからは、苦手なこと、欠点をクリアしていって、ピアノともっと近くなりたいです。ピアノが大好きなのでずっと続けていきたいと思っています。大人になっても弾き続けていけるように頑張ります!
審査員:ラルフ・ナットケンパー氏 (ピアニスト、ハンブルク音楽大学教授)講評
出場者の皆さん、本日はおめでとうございます。支えてくださったご家族にも感謝します。そして、指導された先生がたにもお礼を言いたいです。生徒さんを指導する先生の努力を私はよく知っています。
ピアノを弾く時、例えばそこに「p(ピアノ)」と書いてあるから弱く弾くというだけではなく、そこにどんな感情があるのかを考えて表現しましょう。悲しみのこもった「p」、夢見るような「p」、どういう「p」なのかを考えて表現することが大切です。
また、ピアノは歌のような楽器でもあります。歌うようになめらかに、レガートに気を配って弾くようにしてください。
審査員:今峰 由香氏(ピアニスト、ミュンヘン国立音楽大学教授)講評
今日はたくさんの素晴らしい演奏を聴かせていただきました。
プロのピアニストたちのレパートリーと同じ難しい曲を弾かれていて、これまで多くの時間を練習に注いでこられたと思います。皆さんは、何のために練習をしていますか。指をしっかりと動かす練習やフレーズの作り方などを先生とともに考えたりされていると思いますが、それらを学ぶいちばんの目的は、作曲家の想い、心を明確に伝えるためなのです。コンクールでよい成績を残すためだけに練習するのではなく、楽譜を手掛かりに作曲家の想いを解釈し、舞台の上で豊かに表現し、それをお客さまに伝える、お客さまと分かち合う。それが音楽の素晴らしさや感動につながると思います。
皆さんの素晴らしい才能が、豊かな人生とともに開花していくことを願っています。
「第4回YJPCグランドファイナル」の受賞結果は、オフィシャルサイトでご覧いただけます。