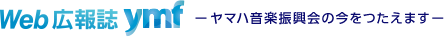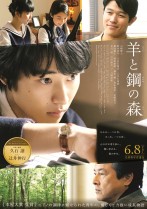2018年6月8日(金)公開の映画『羊と鋼の森』。原作は、2016年第13回本屋大賞を受賞している宮下奈都さんの小説。主人公のピアノ調律師が、ピアノに関わるさまざまな人たちに支えられ成長していく姿が描かれています。
この映画の製作に、ヤマハグループは映画製作スタッフによる「ヤマハピアノテクニカルアカデミー」視察や工具等の貸し出し等で協力を行っています。製作委員会の一人としてこの映画に携わり、ヤマハ㈱ピアノ事業推進部でグローバルのピアノマーケティングなどを担当している田所武寛さんにお話を伺いました。
1台のピアノでつながっている
ピアノ調律の世界は、世間ではあまり知られていないと思います。そもそもどういうことをしているのか?技術者の教育はどのように行っているのか? 昨今、調律師になりたいという人も減っていますが、そんな中で、私どもに映画の製作委員会参加のお話をいただいたとき、映画をきっかけに、とても専門的な、でもやりがいのある調律師という仕事に興味を持ってくれる人が増えるといいなと思いました。
既に小説も読んでいましたが、映画でもピアノを弾く人とそれをサポートする人の人生が、1台のピアノでつながっているのがとてもよく描かれていました。調律師だけでなく、楽器店で働く人、そして家族も。ピアノを通してみんながつながっているように思います。ピアニストも、そういった人とのつながりが背景にあるから頑張っていけるんだろうなと。
音も映像も美しいし、俳優さんも素晴らしいです。ピアノを学んでいる人、これからやってみようかなという人、過去に弾いていた人にも「ピアノっていいよね」「もっと頑張ろう」と思ってもらえるような映画だと思います。
-田所さんがヤマハミュージックヨーロッパポーランド支店で支店長を務めていた2015年、5年に一度の「ショパン国際ピアノコンクール」が開催されました。ポーランド・ショパン協会の公式パートナーとなったヤマハの一員としてコンクールに携わった、貴重なお話を伺いました。-
チーム一丸となって
調律師の花岡昌範さん、現地(ポーランド)スタッフと日々コミュニケーションを取りながら、とにかく「コンテスタントに満足のいく演奏をしてほしい」という思いで、コンテスタントが弾きやすいピアノって何だろう? どういうピアノがショパンに向いているのか? 試行錯誤の毎日でした。ショパンの音楽はポーランドの音楽文化と密接に関わっているので、現地ではどのような演奏が好まれるのかということも、花岡さんはじめ、さまざまな方に助言をいただきながら模索しました。
コンクールがはじまってからは、コンテスタントの練習場所の確保にも奔走しました。嬉しいことに、一次予選前の選定で最も多くのコンテスタントがヤマハのピアノ選んでくれたんです。予想よりも多かったので、急遽、倉庫の一室を片付けて練習室にしたり、ロシア大使館にヤマハのピアノが入っていたので、そこを使わせていただいたり。コンテスタントが風邪をひけば、薬の手配をしたり…。24時間体制で臨みました。
コンクール最終日には、会場で演奏を聴くことができました。花岡さんと隣同士で。コンクールというとメーカー同士の競い合いのように見られがちですが、「全員に1位をとってほしい」「悔いのない演奏をしてほしい」と、祈るような気持ちなんです。これは他社さんも同じではないでしょうか。ピアノの選定から本選まで約1ヶ月強、チームのみんなと奮闘してきたことを思うと感無量でした。ピアノって一人で弾くけれど、実は裏でたくさんの人とつながっている、それがたまらないですね。
-ピアノの魅力について語ってくださった田所さん。実は3歳の頃から「ヤマハ音楽教室」で学ばれていたそうです。次回は、ヤマハ音楽教室での思い出などをお伺いします。-
「Web音遊人」に、田所さんのインタビュー記事「第17回ショパン国際ピアノコンクール-ピアノをめぐる物語」が紹介されています。
映画『羊と鋼の森』公式サイトはこちら