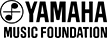研究・レポート
研究・レポート
小川 容子(おがわ ようこ)
岡山大学大学院 教育学研究科 教授
※記事掲載時点の情報です
学問的に「音感(おんかん)」や「良い耳」とは
2013年06月12日掲載 / この記事は約9分で読めます
一般に、音楽をやる上で「音感がある」のは良いことだと思ってらっしゃる方は多いと思います。
音楽の習い事をしている子どもを持つ保護者の方や、音楽を学んでいる皆さん、音楽を楽しむ皆さんの間でも、「○○さんは音感がいい」、あるいは「○○さんは良い耳をしている」といったやり取りは、ごく日常的な会話の中で聞くことができます。
では、「音感」とはどういう意味なのか、「音感がある」とは具体的に何に長(た)けていることなのか――この問いに即座に答えられるでしょうか。
「音感とは絶対音感のことだ」という方がいるかもしれません。しかし、一言で「絶対音感」といっても、それは自然界にある音やテレビから聞こえてくる音まですべて分かることなのか、あるいは音楽大学の受験にあるようなピアノによる聴音ができることなのか、あるいはたとえば「ラ」の音が440Hzなのか442Hzなのか聴き分けられることなのか――実は「音感」は、学術的には極めて説明の難しい言葉なのです。
今回は岡山大学大学院教授 小川容子先生から、この「音感」について3回にわたってレクチャーしていただきます。小川教授は音楽認知心理学、音楽教育学の専門家です。考えれば考えるほど、定義することの難しい「音感」について、学術的にさまざまな見方をご紹介いただき、改めて「音感」というものが何を意味するのか、迫っていきます。
――先日、音楽事典で「音感」を探したら、分厚い事典でも「音感」という項目がないものもありました。実際のところ、この言葉は音楽活動をしている方はもちろんのこと、一般にも流布している言葉と思いますが、「音感」にはっきりとした定義はあるのでしょうか?
小川教授(以下敬称略):「音感」は研究者たちにとっても説明するのが簡単な言葉ではありません。いくつかのポイントを提示しながら、「音感」とはどういうものなのか、順を追って解説していきたいと思います。
まず「音感」という言葉は日本語です。研究者同士で交流するときには、その言葉を英語で何というか、それをきちんといわなくてはいけないというのが、研究者に対して与えられているミッションです。しかし、音感という言葉は、このミッションを達成することがなかなか難しい言葉なんですね。辞書的にいえば、「You have a good ear for music(良い耳を持っている)」という意味になりますが、何についての良い耳か、という問いが生まれますね。
――「耳が良い」という言い回しも、よく使われていると思いますが、「音感」と同様に意味的には漠然としています。
小川:そうですね。たとえば目についても似たような表現があります。「良い目を持っていますね」というと、何を意味しているでしょうか?
――単に「目が良い、悪い」だったら視力のことだと思いますが、「見る目がある」という場合も「良い目」ということになるかと…?
小川:そうです。つまり、「良い目をしている」といったら、ぱっと思いつくのは「視力が良い」でしょう。そのほか、「動体視力がある」「視野が広い」といった測定できる単位での良さをいう場合と、審美眼的なものをいう場合がありますね。偽者と本物を見極める目であったり、ある骨とう品がいつの時代に作られたものかが分かる目であったり、いろいろな「良い目」が考えられます。「目が悪く」なってお医者さんへ行って眼鏡を作るときなどは、視力のことをいいますが、一般に「良い目」というと目利きといいますか、そういうニュアンスで話すことが多いと思います。
しかし、「良い耳」のことを考えるとき、「良い目」でいうところの、偽者か本物かを見分けるという言い回しをあてはめるのは少しつらいかもしれません。「良い耳」についての話をしようとして、そういうふうに対応できるかというと、意外にできないんです。
もちろん、「今日の演奏は、ちょっといまいちだったよね」「やっぱりベルリンフィルはいいよね」というような「良い耳」に関するいい方もよく使われます。でも、それは一般的な使われ方ではありません。さらに専門家の中では、「ピッチが442Hzじゃなかったよね」といういい方をしたりしますが、このときの「良い耳」とは、審美眼的な判断ができる耳というより、聴力の方が問題になってきます。
――確かに、視力が良いことと、審美眼が優れていることは話題として明確に分けて考えることができそうです。でも、日頃の生活の中で「良い耳だよね」といわれたとしても、聴力が優れていることをいわれたとは思わないし、他方、素晴らしい演奏を聴く耳のある人は、音の高さや大きさといった要素も聴き分けているので、聴力も関係していそう…。難しい問題です。
小川:だから、研究者は「耳の力」といったときに、とりあえず測ることができる力に焦点をあててそれを測ってみようと、そこから考えていこうとしたわけですね。
――「音感」が外国語には置き換えられない言葉であること、「良い耳」といってもさまざまな意味を指す可能性があることは分かりました。それでは、先生のご専門である音楽心理学の領域で、研究者たちは「耳」をどのように扱ってきたのですか?
小川:それは、音楽心理学の歴史とかかわってきていることといえますね。そもそも「心理学」は学問の世界の中で、初めは非常に危ういものだったんです。たとえば哲学や数学といった、ほかの先行している学問に比べて、「錬金術や星占いなんじゃないの」っていわれてしまうような危うさがありました。
――錬金術ということは…卑金属を黄金に変えようとしたり、不老不死の万能薬をつくり出そうとした技術のことですよね。科学的な観点からするとオカルトのような側面が見られますが、そういう印象を持たれていたということなら、確かにつらいです。
小川:心理学者は肩身が狭い思いをしながら、何とかほかの学問に対抗するために、最初は動物を使った研究から始めました。たとえばイワン・パヴロフ(Ivan Petrovich Pavlov)などは、犬やマウスを使って実験し、いろいろな形でエビデンスを求め、データを積み重ね、「心理学もなかなかだ」ということを知らしめていったわけです。
しかし動物実験ばかりだと、結局は「動物心理学なの?」といわれてしまうので、次第に人間を対象とする領域へ向かっていきました。最終的に「人間は何を考えているのか」というところに行き着くまでに、まずは「人の目とは」「人の聴覚とは」など、感覚心理学から入っていったのです。たとえば、人はどの程度熱いものに耐えられるのか、目はどのくらい遠くまで見えるか、人はどのくらいの大きさだったら聞こえるのか、音と分かるのか、などです。
耳が持つ特性のある種の限界と、心理学という学問の持つ歴史的な経緯、この2つの側面があって、「良い耳とは」という問いに対峙するわけですから、まずは「聴力」がテーマになってくる、これが大前提としてあると思います。何となく納得がいくのではないでしょうか。
――きちんとエビデンスを示すことができる可能性の高い「耳の力」をテーマに、研究が始まったということでしょうか。
小川:はい、そうです。まず「聴力」のところをどう考えようか、というところで、「音楽の耳の力」に関して、私たちはどのくらいのピッチの差であったら弁別ができるのか、2つの音が同じか違うか区別することが可能なのか、あるいは和音がいくつの音から構成されているか聞き取れるか、こうした試みから始まりました。
――シーショア の研究ですね。彼は2つの音を聴いて、それらの高さの違いなどを弁別できるかどうか調べる音楽テストを作ったと本で読んだことがあります。確か初めのテストは1919年のものだったので、100年近く前のものになりますね!
小川:このシーショアの研究が、音楽心理学の中で聴覚を集中的に取り上げた聴覚心理学研究の始まりともいえます。それで、「聴覚心理学=音楽心理学」みたいな構図が出てきてしまったといいますか、時代がそこを求めていたということがあると思いますね。その頃から、耳についてのいろいろな議論が起こってきます。
たとえば、ある耳の力に関して音楽テストを使った実験が行われると、そんなテストで耳の何が分かるのかと指摘される、それで別のテストができてさらに論争が巻き起こる、その繰り返しです。同時に、音楽テストをやって、音楽の何が分かるのかという論争も起きてきます。ある研究者は「基礎的な能力」を測るテストだといい、別の研究者は「音楽能力」ではなく「音楽適性」を測っているんだといったり、または「音楽性」に関する研究だといったりします。
そうした中、アメリカのゴードンが、長期にわたってこの研究を展開することになります。
――ゴードンが発表した音楽テストは、非常によく知られていますね。実は私もテストの中身を聴いたことがあるんです…。小川教授には「音感」から始まり、耳の力をどうとらえるかについてレクチャーをしていただきましたが、次回はこのゴードンによるテストの話題から、引き続き私たちの耳について、お話していただきます!
- ※ Pavlov, Ivan Petrovich(1849 – 1936)。ロシアの生理学者で1904年にノーベル生理学医学賞を受賞。条件反射の現象を発見したことで有名。アメリカの行動主義心理学に大きく貢献した。
- ※ Seashore, Carl Emil(1866 – 1949)。アメリカの心理学者で1919年に音楽才能テストを発表、その後1939年と1960年には改訂版も作った。
聞き手:ヤマハ音楽研究所研究員 小山文加(おやまあやか)
著者プロフィール ※記事掲載時点の情報です
小川 容子(おがわ ようこ)
岡山大学大学院 教育学研究科 教授
専門:音楽教育、音楽認知心理学
著書・論文
- 音楽する子どもをつかまえたい:実験研究者とフィールドワーカーの対話 2008年,ふくろう出版
- 音楽教育学の未来 -日本音楽教育学会設立40周年記念論文集 2009年,音楽之友社
監訳書
著書・論文
- 音楽する子どもをつかまえたい:実験研究者とフィールドワーカーの対話 2008年,ふくろう出版
- 音楽教育学の未来 -日本音楽教育学会設立40周年記念論文集 2009年,音楽之友社
監訳書
今後より一層内容の充実を図るため皆さまからのご意見・ご要望をお聞かせいただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。(全12項目)