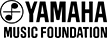研究・レポート
研究・レポート
小川 容子(おがわ ようこ)
岡山大学大学院 教育学研究科 教授
※記事掲載時点の情報です
音楽的な行動の土台には…
2014年03月31日掲載 / この記事は約10分で読めます
岡山大学大学院教授 小川容子先生による「音感」をテーマにしたレクチャーシリーズの第3回。前回は、国際的に知られる研究者・教育家であるゴードンのつくった音楽適性プロフィールや、小川先生の発表した新アジア版音楽適性テストなど、音楽テストについて紹介していただきました。
さて、音楽テストではピッチ(音の高さ)の違いを聴き分けられるかどうかを問われることがあります。「ピッチがわかる力」から「絶対音感」という言葉を連想される方もいらっしゃるのでは?しかし小川先生によれば、音楽に親しむ上で絶対音感の有無は一つの側面にすぎず、音感の有無とはあくまでも別のお話とのことでした。今回は、この「絶対音感」に関するお話の続きからうかがいます。
――絶対音感があることと音感が豊かであることは別の問題とのことですが、会話の中では「絶対音感」と「音感」という言葉が同義に用いられる場面も多いように感じます。かつて『絶対音感』※1がベストセラーになったのも、絶対音感に対する関心の高さの表れともとれると思いますが、いかがでしょうか?
小川教授(以下、敬称略):「絶対音感」も「音感」も何か特別な力であるようなイメージが先行して、混同されてしまっているところがあるのかもしれませんね。しかし前回お話ししたように、絶対音感と音感は別の問題ですし、一言で絶対音感といっても、それは「程度」や「幅」を持っています。
音楽にもさまざまな活動のフィールドがあります。たとえばレコーディングの世界を考えてみましょう。そこでディレクターやエンジニアの方々は、耳の力そのものを試されています。『音の感性を育てる―聴能形成の理論と実際―』※2という本では、録音技術の専門家を対象に行った聴能テストの実験などについて紹介されていて、聴能形成のための課題を収めたCDも添付されています。この本では「聴能」という言い方がされていますが、シーショアやゴードンの路線より更に突き進んだ形のものです。こうしたお仕事のエキスパートを目指すならば必要だろうとされる、聴き分ける「力」が示されています。
――専門的な用語を使えば、音圧レベルの差を弁別したり、特定の周波数帯域を強調した音楽を用いて、どの周波数帯域が増幅させられたのかを判定したりする問題がありますが…。「ド」と「ド#」、フォルテとメゾ・フォルテといった違いを聴き取る以上のことが問われています。音の高さがわかる人であっても、ここに提示される2つの音源の違いを聴き比べることはかなり難しいのでは?
小川:はい、絶対音感の持ち主だとしても、これを聴き分けるのはとても難しいでしょうね。しかし、これも「音感」の一つと言えるでしょう。音響技術に関するエキスパートや特殊な領域になると、こういう細かいところまで聴き分ける力が求められることもあるということです。つまり、音の聴き分けにおいて目指すべき力は、何を対象とするかによって変わってきます。
もし、将来スタジオで音響関係の専門家になりたいと願うならば、ここまでやっていただく必要があるかもしれません。しかし、これほどのレベルを求めていない場合がほとんどでしょう。求められるレベルは状況によっても変わってきますし、指導者側の判断による部分もあると思います。音感とは何をどこまで聴き分ける力なのか、広げようと思えばどこまでも広げることが、深めようと思えばどこまでも深めることができるのです。
音感の構成要素を探る→「できていること」の背景に音感を読み取る
――音感をめぐる近年の研究の状況はどのようになっているのでしょうか?
小川:ここ10年ほどの先行研究から、いくつかの方向性が指摘できると思います。まず、日本でも世界でも、新しい音楽テストを開発する、あるいはゴードンなどの既存の音楽テストを用いるような研究が主流だった時代は過ぎ去ったと言ってよいでしょう。というのも、音楽テストの点数が高ければ音楽を深く理解したことになるのかという疑問が根強くあるためです。ゴードンの音楽適性プロフィールで良い点数をとったとしても、音楽大学に入れるとか将来音楽家として成功するといったこととは無関係、ということですね。
――音楽テストという手法が主流でなくなったということは、何を意味するのでしょうか?
小川:「音感とは何から成り立っているのか」という観点から、音感を幾つかの構成要素に切り分け、音楽テストで点数を測るという研究手法が、ある程度のところまで行き着いたと考えられます。昨今の研究スタイルの一つとしては、音楽テストを他のテストと組み合わせて関係性を探るものがみられます。たとえば音楽家と非音楽家(non-musicians)の情報処理のスピードを検討する研究があります ※3。ここでは音楽家と非音楽家というグループのスクリーニングに音楽テストが使われていて、ゴードンのテストにおける点数の違いが示されています。
――音楽テストを開発するより、それをスクリーニングに活用して研究が進められているのですね。
小川:また、最近の研究というのは、音感の構成要素を探る時代とは逆の流れになっています。それは、音として鳴り響く音楽行為に対して、行為そのものを文脈から丸ごと探りましょうという研究の流れです。
たとえば「歌を歌うことができる」というとき、「何かができているから、歌が歌える」と捉えます。構成要素から入るのではなく、既に実現されている行動から、「なぜそれができるのか」「ある状況下にあるからできているのだろうか」と考えて関係性を見つけ出していくんですね。このような研究では歌を歌えることであったり、ピアノが弾けることであったり、スポットをあてる部分が一場面や一つの状況に限定されることもあります。文脈を探ることで諸要因の関係性が浮き彫りになりますから、その要因が「音感だけ」という結論は出てこない。けれどアプローチによっては、そこから推測することはできます。
――推測といいますと?
小川:たとえば、「歌うことができる」ということにはいろんな考え方がありますが、2010年に発表されたある論文では、歌うには最低限、次の三つができればよいという考え方が提示されていました※4。きちんと正確なピッチをコントロールできること、声域があること、調性をとらえることです。先生の歌声を聞いてきちんと音の高さをわかるようになった、声域が広がった、調性感が豊かになった…、こうして歌が上手になったとすれば、これらを音感の一つだと言うこともできるでしょう。ここでは「音感」という言葉は全く出てきませんが、そういう捉え方、つまり研究者のスタンスを読み取ることができます。
――音感として定義付けるのではなく、読み取っていくということですね。
小川:「音感」という網が広がっていくとイメージしていただけたらいいと思います。できたことの結果から「このようにも読み取れる」という形で研究していく、これが現在の音感や音楽能力を取り巻く研究の進め方です。正しいピッチで歌うこと、テンポを刻むことなど、フォーカスがとても狭いところに当たっている分、説得力があります。そして、扱っているのはとても限定された範囲のことだけれども、その背景に豊かに広がっているであろう、音楽行動のベースとなっている土壌や基礎的な力を考えると、それを音感という言い方に置き換えることができるでしょう。
――本シリーズでは3回にわたって、「音感」を定義付けることの難しさに加え、学術的研究の成果に基づく、さまざまな視点からの音感の捉え方、考え方をレクチャーしていただきました。ただ、音感という言葉の意味が曖昧なままであっても、指導者である先生が保護者の方から音感について質問を受け、説明を求められるケースも現実的にあるかと思われます。ぜひ最後にアドバイスをお願いします!
小川:そうですね。学校でもピアノのレッスンや音楽教室でも、先生方が保護者の方から音感について質問されて、それにどう答えるか悩んだという話を聞いたことがあります。そこで発想を転換して、研究者が保護者の方と緊密に協力・連携し、子どもの音楽行動を共に調査する研究も試みられています※5。
繰り返しになりますが、音感に絶対的な定義はありません。歌を歌っていてきちんとピッチ・コントロールできたらそれを音感と言うことはできるでしょう。絶対音感と音感はイコールではありませんが、ピッチが分かることも音感の一つ、リズム感や、お友達と合わせて演奏できることも…どれも一つの音感と捉えられます。どれも大事ですけれども、すべてが必須ではないし、どれかだけに特化するものでもないでしょう。それは自分が何を目指すかによっても変わってきます。
「音楽の聴き方」はよく議論のテーマになりますが、そもそも私たちはみんな日々の暮らしの中で音楽を聴いていますし、聴くことは、みんなできます。ただ、どのように聴くべきか、教わらないと分からないこともあります。一番耳につきやすいのは、強弱やテンポの違いといった局所的・表面的なものですね。何かを深く追いかけて、じっくり聴くことができるというのはすごいことです。ここにフックをかけたらいいのだと、一つのきっかけがあれば他のきっかけもつかめるかもしれません。面白いから聴く→聴くと別の面白さに出会う→もっと聴きたくなる…こういう循環がつくれるといいですね。ずっと音楽を続けてくれるかどうかについては、動機付けの大切さも見過ごせない要素になっています※6。
――私たち一人ひとりにとって、音楽を続けたり、楽しんだりしていくプロセスにおいて重要な音感とは何か、考え方や目指すものはさまざまなのかもしれません。3回にわたり、多角的な視点から「音感」を捉え直すヒントに満ちたお話、どうもありがとうございました。
- ※1 最相葉月『絶対音感』小学館、1998年。小学館ノンフィクション大賞受賞作品で、現在では文庫版も販売されている。
- ※2 北村音一、佐々木実監修、岩宮眞一郎、大橋心耳編『音の感性を育てる―聴能形成の理論と実際―』音楽之友社、1996年。
- ※3 Bugos, J., Mostafa, W. (2011, Winter). Musical Training Enhances Information Processing Speed, The Bulletin of the Council for Research in Music Education, 187, 7-18.
- ※4 Hedden, D. G., Slattery, V. (2010, Spring). Perceptual and acoustical analyses of second graders’ pitch-matching ability in singing a cappella or with piano accompaniment, The Bulletin of the Council for Research in Music Education, 184, 35-48.
- ※5 Valerio, W. H., Reynolds, A. M., Morgan, G.B., McNair, A. A. (2012). Construct Validity of the Children’s Music-Related Behavior Questionnaire, Journal of Research in Music Education, 60(2), 186-200.
- ※6 たとえば、高校生を対象とした、音楽を続ける要因に関して質問紙を用いて調査した研究では、誰かから褒められたりすることよりも、自分が好きだからやるのが当たり前だというような動機付けの重要性を示唆している。(MacIntyrem, P.D., Potter, G. K., Burns, J. N. (2012). The Socio-Educational Model of Music Motivation, Journal of Research in Music Education, 60(2), 129-144.)
聞き手:ヤマハ音楽研究所研究員 小山文加(おやまあやか)
著者プロフィール ※記事掲載時点の情報です
小川 容子(おがわ ようこ)
岡山大学大学院 教育学研究科 教授
専門:音楽教育、音楽認知心理学
著書・論文
- 音楽する子どもをつかまえたい:実験研究者とフィールドワーカーの対話 2008年,ふくろう出版
- 音楽教育学の未来 -日本音楽教育学会設立40周年記念論文集 2009年,音楽之友社
監訳書
著書・論文
- 音楽する子どもをつかまえたい:実験研究者とフィールドワーカーの対話 2008年,ふくろう出版
- 音楽教育学の未来 -日本音楽教育学会設立40周年記念論文集 2009年,音楽之友社
監訳書
今後より一層内容の充実を図るため皆さまからのご意見・ご要望をお聞かせいただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。(全12項目)